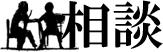 相談
相談
どうしてわたしには彼氏ができないのかな、と蒔絵が言った。
「……えーと。ごめん、いきなり何?」
悠太は聞き返した。ついさっきまで覆面プロレスラーをテーマに盛り上がっていたのに、唐突にあんなことを言われたら誰だって面食らうだろう。文芸部の部室には蒔絵と悠太の二人だけだから、ひとりごとでなければ、それは悠太に向けた質問だということになる。
「あ、ううん。ごめんね。答えにくいよね。わたし、分かってるの。本当のわたしを好きになってくれる人なんかいないってこと――」
「え? ん? いや、違くて。文脈というか脈絡というか――」
「わたし、自分ではけっこうイケてる方だと思ってるんだよね」
「プロレスの話は? もういいの?」
「別に自慢するわけじゃないけど……何度か、その、男の人に告白されたことだってあるし」
「あ、そう。うん、分かった。蒔絵さん、ほんとはその話がしたかったんだね。ごめんね、僕がいきなり覆面レスラーの話題振っちゃったから」
「でもわたし、いざ男の人に告白されるとね、ちょっと怖くなっちゃって……。勇気がなかったのかな。あの人がバツイチで子持ちだからって、ためらうことはなかったのに」
「こ、子持ち? えええ、ってことは生徒じゃないよね。せ、先生?」
「ううん、後悔はしてないの。あの人の目的は、わたしの体だって分かってたから……男の人はみんな、わたしの外見しか見てないから……」
「蒔絵さん何気に自信家だよね」
「美しいというのは罪なのね……」
「蒔絵さんはたしかに可愛いけど、そこまで可愛いわけじゃないから、蒔絵さんの罪は軽いと思うよ。せいぜい罰金刑だよ」
「どんなに顔が綺麗でも、良い事なんかひとつもない。わたしの心を理解してくれる人がいないもん。はあ……悠太くんが羨ましい。悠太くんのことを好きな女の子がいたとして、その子が悠太くんの外見に惹かれた可能性はまるでないもんね」
「いつも思うけど蒔絵さんは辛辣だよね。彼氏ができない理由、心当たりない?」
「あーあ。どこかにわたしのことをよく分かってる男の人がいないかな」
「まず猫をかぶるのをやめるべきじゃないかな。クラスのみんなは騙されてるみたいだけど」
「それから趣味が合って」
「今はプロレス好きの人ってあんまりいないからね」
「わたしのことを受け止めてくれる人」
「よっぽど心が広い人じゃないと無理だと思うよ。蒔絵さん、天然っぽいし」
蒔絵が悠太のことを睨みつけた。
そのとき、蒔絵の頬がわずかに赤くなっているのに気づいた。
「な、何?」
「どうして悠太には彼女ができないのかな?」
「え? ……さ、さあ。なんでだろ」
「鈍感だからよ」
蒔絵はそっぽを向いた。
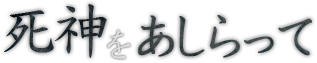 死神をあしらって
死神をあしらって
僕は夢の中で死神の女の子に襲われていた。
女の子の振りかざした鎌を避けて脇腹に崩拳を叩き込んだところで目が覚めた。
目が覚めるとベッドの上にいた。意識が戻ってから数分後に目覚ましが鳴った。起床の時間なので僕は起きることにする。この後は三十分で朝食を済ませ、次の三十分で登校の準備をするのが日課だ。
ベッドから足を下ろしたとき、妙な感触があった。
下を覗くと黒い服の女の子がうつ伏せで倒れていた。そばには柄の短い三日月のような刃の鎌が落ちている。
「うにゅ……」
踏んだ拍子に女の子が小さく声を漏らす。女の子の相手をする日課はなかったので、僕は女の子をその場に残してキッチンへ向かう。
トーストを食べ終え、コーヒーを飲んでいたときに女の子がリビングに飛び込んできた。
「あ、あなたの命、頂戴――!」
叫びながら鎌を振り下ろす。
僕は素早く女の子の懐に飛び込むと、鎌を避け、女の子の側頭部にフックを打ち込んだ。
女の子は倒れた。
「……さて」
僕は朝食の後片付けを素早く済ませると顔を洗って歯を磨いた。
学校の制服に着替え終わったころ、リビングの女の子が起き上がった。
「あの……あなた、少しはわたしという存在に疑問を持ったりしないのでしょーか……?」
「僕の知能を使う価値のない問題だ」
「うう……」
女の子は涙目になったが、学校に行く時間なので無視する。
鞄を持って玄関へ行く。女の子は僕の後ろについてきていたが、これからの行動に支障はないので無視することにした。
僕は玄関のドアについているチェーンロックと南京錠とディスクタンブラー錠二つとドアガードを開けて外に出る。
「あの、何でこんなに鍵がついているんですか……?」
「留守の間に公安が僕の部屋に入れないようにするためだ」
「その家の中に、わたしがいたという事実に、何か思うところはないのでしょーか……?」
「もっと鍵を増やすことにする」
学校に向かって通学路を歩いていると、後ろにいた女の子が僕の隣に来て並んで歩き始めた。
「あ、あのっ! ……わたし、死神です。あなたの命を刈り取るために来ました」
「そうか。僕は人間だ。学校に行くために歩いてる」
「夢の中のこと、覚えてますか。あなた、わたしにあんなことをしたから、こっちの世界に落ちてきちゃって……」
「そうか。勝手に僕の家に入ってことについては不問にしてやる」
「うう……わたし、あなたにとって取るに足らない存在ですか? そりゃあわたしは、あなたに比べれば個性がないですけど……。そんなに死神っぽくないですか?」
「……きみが死神なのは、夢の中で会ったときに分かっていた。だから言ったはずだ、僕の知能を使うまでもない、と」
女の子は少しの時間キョトンとしていたが、やがて引きつるように頬を緩ませると、そっぽを向いて僕に顔を見せないようにした。
「そ、そうですか……死神っぽいですか……ぅへへ」
女の子が僕に鎌を振り下ろした。
喉にチョップを当てた。
女の子は倒れた。
僕は学校に行った。
 空を跳ぶ少女
空を跳ぶ少女
ミサオが目覚めたとき、時計を見るといつもならとっくにアパートを出ているはずの時間だった。一時間前に鳴るはずだった目覚まし時計が枕元に静かに佇んでいた。記憶はなかったが、どうやら目覚ましを止めて二度寝していたらしい。大学の講義が始まるまではまだ時間があったが、バスの出発時刻はとうに過ぎていた。
本日一限目の講義は線形代数学で担当は棚星先生。とにかく時間にうるさい先生で、講義が始まって五分以内の着席であれば遅刻だが、それ以降は問答無用で欠席にされてしまう。そしてミサオは遅刻と欠席の常習犯だった。もう出席数はぎりぎりで、これ以上さらに欠席を重ねる余裕はとうに残っていなかった。
あの退屈で実のない講義を来年も履修するのはまっぴらごめんだ。たとえバスに間に合わないとしても、講義が始まる前には何としてでも大学にたどり着かなければならない。
悠長に考えている時間はなかった。ミサオはナップサックを背負い、ボロボロのスニーカーを履いてアパートを飛び出した。
ミサオがいつも乗るバスは市内をぐるりと回るルートで大学へ向かう。実際の直線距離で言えばアパートと大学はそれほど離れてはおらず、ミサオにとってはそこが狙い目だった。
ミサオはアパートを出てまっすぐ正面に飛び出した。向かいの平屋住宅のブロック塀が迫ってきても、減速することなく走り続ける。
ブロック塀に衝突する直前、ミサオは跳び上がると、ブロック塀のわずかな出っ張りに右足を引っ掛け、次に左足も引っ掛けて、右手を伸ばしてブロック塀の上を掴む。
勢い良く体を持ち上げて塀の上に両足を乗せると、それを足場に前方へ飛び、民家の屋根に飛び移った。
屋根の上を走ると瓦が鳴った。視線の先にある靴屋の屋根までの距離を一瞬で測った。
建物の間にある塀と右隣の民家の壁を順に足場にし、三段目に靴屋の二階の壁に足を引っ掛け、そこから屋根の縁に手をかけて壁を登り切った。
さらに屋根の上を駆け抜けて、隣の倉庫のトタン屋根に飛び降りて――。
ミサオは生まれつき身体能力に恵まれていた。
中学の頃にはもう屋根の上を跳び回りながら登下校をするようになっていた。普通に歩けば二十分はかかった通学路が、ミサオのルートでは十分で登校することができた。この登校は、危険だからと両親に禁止されるまで半年ほど続いた。
禁止されてからも、授業や待ち合わせに遅刻しそうな日は両親の目を盗んでこっそりと「跳び回って」いた。
ミサオは工場の屋根から走り幅跳びの要領で飛び降りた。道路に停車していたトラックの屋根を足場に、そばの事務所の窓に指を引っ掛けて飛び上がる。猿のように両足を同時に動かして一階分の壁を駆け上がった。
そこからさらに隣の建物の屋根に飛び降りるように移動するとき、意味もなく前方宙返りをして楽しんだ。自分の体の軽やかさに、鼓動が早くなった。
マコトは大学に向かうバスの中で窓の外を眺めていた。
一限目の講義は線形代数学だ。去年の期末試験の問題はサークルの先輩から入手済みだ。遅刻や欠席さえしなければまず単位は取れるだろう。
退屈だ、とマコトは思った。
意識に薄い膜を張ったような状態がずっと続いていた。現実のすべてがどうでも良かった。現実にまったく興味がない。目の前の現実をぼんやりと見ているだけ。マコトにとっての大学生活は、バスの窓から景色を眺めるのと同じだった。自分のことにまったく関心がなかった。
そのとき、ぼんやりとした意識が、窓の外のある一点に収束した。
やがてその光景の意味を理解すると、一瞬で意識が覚醒した。
――女が屋根の上を跳び回っていた。
建物の屋上と屋上の間を、ゲームのように跳んで移動している。隙間の大きな場所であろうと、間にあるものを何でも足場にして通り抜けてしまう。いかなる障害物も、その女を一秒と足止めすることができなかった。
マコトはしばらく女を凝視していて、はっとした。女は同じ大学に通う遊川ミサオだった。
遊川と会話したことは一度もなかったが、大学の中庭でブレイクダンスをしていたのが印象に残っていた。
休み時間いっぱいにブレイクダンスを踊った後の、満足そうな遊川の笑顔を思い出した。
屋根の上を跳び回る彼女がその目的地に着いたとき、いったいどんな表情をするのだろう。
マコトの鼓動が早くなった。
遊川がバスのすぐ近くまで来た。道路に飛び降りてバスの前を横切る。運転手が慌ててブレーキを踏む。彼女は街路樹や歩道の手すりを足場にあっという間に建物の屋上に登ってしまった。
マコトは立ち上がった。運転席に向かう途中、マコトに声をかけようとしていた同級生がそばで固まっていたが、遊川のことしか頭になかったマコトは気が付かなかった。
「ここで降ります! 降ろしてください!」
気圧された運転手が慌ててバスのドアを開けた。運賃箱に小銭を放り込むと、マコトはバスを降りて遊川の跳んでいった方向に駆け出した。
ノノカは一日の大半の時間を宇田川マコトのことを考えて過ごしていた。考えるだけでなく、実際にマコトのために行動を起こしていた。ノノカはマコトのストーカーだった。
マコトは幼なじみだった。家が近所だったので、物心つくころには二人は自然と仲良くなり、当時のノノカはマコトの後ろをずっとついて回っていたらしい。
小学校にあがったころから徐々に疎遠になり、ノノカが中学に入学した年にマコトは引っ越してしまった。
マコトと再会したのは大学の入学式だった。
ノノカは一目見ただけで彼のことが分かった。しかしマコトはノノカのことを思い出せなかったようだ。何度か言葉を交わしたときも、マコトはただの同級生としてノノカに接していた。
マコトに、自分のことを思い出して欲しかった。
でも声をかける勇気はなかった。
大学の講義中、自然とマコトのことを目で探していた。休み時間、自然とマコトのことを追いかけていた。講義が終わりサークルに行くマコトの様子をさり気なく伺ったりした。
……気づいたときには、ノノカはずっとマコトの後を付け回していた。
偶然にもマコトのアパートはノノカのアパートの近くだった。大学に行くには同じバスで向かう。学科が同じなので授業も一緒になることの方が多い。ノノカはサークルには入っていなかったが、講義が終わってから大学に留まるのは別におかしなことではないし、何となくサークル活動を眺めるのも自然なことだろう。アパートが近いのだから帰りのバスが一緒になることだって十分にあり得る。
――と、自分がストーカーではない理屈はいくらでも積み上げられる。しかし自分がやっている行為が客観的に見ればものすごく気持ち悪いということをノノカは十分承知していた。さりとてこの思いを諦めることもできなかった。
もうこうなったら、勇気を出して話しかけるしかない。と、頭では結論を出していたのに、実際に声をかけようとすると足がすくむ。
しかし、それもこれまでだ。今日こそは声をかける。結果がどうであろうと後悔はしない。そしてマコトのストーカーも今日できっぱり辞める。
朝、大学に向かうバスの中で、いつものようにマコトを見つけた。
後ろの席を確保する。物憂げな顔で窓の外を眺めるマコトの姿に鼓動が早くなった。
ノノカは自分の頬を叩いた。痛みが意識をはっきりとさせる。大きく深呼吸を繰り返してから、席を立った。
マコトの座席に近づく。声をかけようと、口を開いた。
そとき、バスの前を何かが横切った。運転手がブレーキを踏む。ノノカは倒れそうになり、慌てて吊り革を掴んだ。
マコトの目はバスの前を横切った何かを追いかけていた。
彼は突然立ち上がった。運転手に詰め寄ってドアを開けさせると、運賃箱に小銭を投げ入れてバスを飛び降りた。
ノノカのことは気にも留めなかった。
棚星には心配事があった。娘のノノカのことだ。
棚星は大学の研究者で、講義では主に数学を教えていた。棚星の大学に娘のノノカが入学したのは今年の春のことだった。
素直な娘だった。幼いころに両親を失くし、数年前に妻を失くした棚星にとって、ノノカだけが唯一血のつながりのある存在だった。
だが入学式の日、娘はどこか様子がおかしかった。
その日だけでなく、今日に至るまでずっとおかしな状態が続いている。
まずは帰りが遅くなった。それも「頻繁に遅くなる」というレベルではなく、毎日遅いのである。娘がサークルに入っていないのは知っている。友達と遊ぶわけでもなく、かと言って勉強をしている様子もない、毎日毎日どこで何をしているのかを問いただしても、娘から返ってくるのは曖昧な答えばかりだ。
また、講義中には頻繁によそ見をしていた。素直で真面目なノノカの性格を知っている棚星には信じられないことだった。
今日は朝一で線形代数学の講義があった。ノノカもこの講義を履修している。
棚星は開始時間ぴったりに出席者の確認を行った。いつも一番前の席で受講している宇田川という生徒が来ていないのが気になったが、いくら講義のことを考えようとしても娘のことが気になる。黒板に数式を書きながらも、意識は常に娘の様子を伺っていた。
ノノカは目に見えて元気がなかった。よそ見をするでもなく、ただ前を向いてその場に座っているだけのように見えた。
――今朝、何かがあったのだ。
脳裏に様々な「悪い」想像が駆け巡った。不安で心臓の鼓動が早くなる。
高校に入ってから棚星は娘との接し方が分からなくなっていた。たまに会って話すときも、他人と会話をしているようなよそよそしさを感じることがあった。
そのとき派手な音を立てて教室のドアが開いた。入ってきたのは遅刻の常習犯、遊川ミサオだった。
「セーフっ!」
「遅刻だ」
棚星が言うと、遊川ミサオはその場に崩れ落ちた。
 300円の幸福
300円の幸福
お盆になると、寮の学生はみんな実家に帰ってしまう。
実家に帰らないのは僕と真西くらいのものだろう。
真西は経済学部の二回生で、三回生の僕よりも後輩だったが、彼女は一浪した上に一回生の丸一年を休学しているので、実際は僕よりも年上だった。
僕は真西が苦手だった。
何というか、無防備すぎるのである。いや、無防備なだけならいい。僕は僕の関係のないところでどれだけたくさんの人が不幸になろうとも気にしない人間だ。しかし真西の場合は僕にかなり接近してくる――つまり馴れ馴れしく接してくるので、世の中の悪意をまったく信じていないらしい彼女を見ていると、こう、保護欲を駆り立てられるというよりは、危なっかしくて見ていられなくなるのだ。
そうだ、真西のことを評するに「危なっかしくて見れいられない」という表現ほど的確な言葉はないだろう。
寮に他の学生が戻ってくるのはいつになるだろう。お盆は管理人すら帰省していなくなる。
僕は不安だった。
二人きりになった三日後には真西は朝から僕の部屋に入り浸るようになっていた。
今、彼女は僕のベッドを占領して仰向けになって漫画を読んでいる。茶色に染めたポニーテールがベッドの端から下に垂れていた。
「あの、真西さん」
「真西でいいよ、佐倉センパイ。だって私の方が後輩じゃん」
「その漫画が読みたいなら貸すから、自分の部屋で読んだら?」
「えー、いいじゃないっすか。センパイの部屋、居心地いいんですよ。漫画あるし、掃除もしてあるし。あとご飯も出るし」
「僕の部屋はホテルじゃないぞ」
真西はパタン、と漫画を閉じた。
やっと帰ってくれるのかと期待したが、もちろんそんなはずはなかった。
「センパイ、私お腹が空きました」
「コンビニならここから徒歩で10分くらいのところにありますよ」
「センパーイ、何か作ってくださいよー」
「いい加減にしてくださいよ真西さん……。気づいたら僕、お盆に入ってから、真西さんの三食全部作ってるじゃないですか」
「お腹すいて動けないー部屋に帰れないーもうここで暮らすー」
駄々っ子のように手足をジタバタさせる。
しかたがないので昼飯を作ってやることにした。いつものパターンだった。だから僕は真西が苦手なのである。
しかし昼食を作るといっても僕は料理なんてほとんどできない。それにもかかわらず外食をせずにいつも自分で作るようにしているのは、第一にお金がないのと、第二にこの近辺にはまともな値段でまともな料理を提供する店が存在しないからだ。
僕は共同の台所に行くと、お湯を沸かして即席麺を茹でた。その間にもやしとキャベツを炒めて、スープに麺と野菜を入れれば完成だ。
「待ってましたー!」
いつの間にか台所に来ていた真西がパチパチパチと手を叩いた。
僕と真西が、それぞれのドンブリを持って僕の部屋へ移動した。
「……ちょっと待って。なんで僕の部屋に来た?」
「一緒に食べた方が美味しいじゃないですか」
何の疑問も抱いていない表情でそう言って、僕の部屋の食器入れから自分の箸を出して、ずるずるとラーメンをすすった。……気がつくと、彼女の箸も、コップも、ドンブリも、みんな僕の部屋に置くようになっていた。
「ねえ……いい加減自分で作ろうよ」
「センパイの料理が食べたいんです。はい、これ食事代」
「……こんなにもらえないよ。このラーメン、300円もかかってないよ」
「私にとっては300円以上の価値がありますよ。ま、心付けです」
真西は僕のポケットに千円札をねじ込んだ。こんな貧しい寮に住んでいるくせに、彼女はこれでも結構な金持ちなのだ。親が建設会社の社長だとか何とか。
「……こんなラーメン、誰が作っても変わらないだろ」
「でも私、センパイが作ったって思うと、誰が作ったご飯よりも美味しく思いますよ」
僕は顔が熱くなった。
それはどういう意味だ――とは聞けなかった。それを聞くと、後戻りできなくなる気がする。そういえば、真西が僕以外の人間に馴れ馴れしくしているところを見たことがない。
何も言えなかったので、黙ってラーメンをすする。
不味かった。
 吾輩こそが猫である
吾輩こそが猫である
巷では猫を主人公にした読み物があると聞くが、あんなものは人間が猫のことを勝手に想像して書いた紛い物に過ぎない。吾輩こそが本物の猫であり、諸君らが読むべきは吾輩の語る物語である。
名前はすでにある。吾輩の世話をしている女は吾輩のことを「ローラ」と呼ぶ。こんな名前で呼ばれているが、吾輩はオスである。これは、吾輩の性別を確認する前にそんな名前をつけた、あの女が間抜けだったのだ。
猫は仕事をしない。だから吾輩も仕事はしない。毎日寝そべりながら、餌の時間に餌を食べるだけの毎日だ。
人間は吾輩の生活を羨むだろうが、ただ食べて寝るだけの生活というのもそれはそれでつらいものがある。とにかく退屈なのだ。
吾輩の暮らしには自由がない。吾輩が寝起きしているのは石で作られた小さな丘の上で、その周囲は壁と柵でぐるりと覆われていて、外に出ることはできない。無論、外に出たところでここより楽な暮らしは望めないのだから、頼まれても出て行くつもりはないのだが。
あくびをしながら丘の上で寝そべっていると、壁の上から人間たちがじろじろと吾輩のことを眺めている。こんな猫一匹の何が面白いのかは分からないが、子供も大人も、毎日大勢の人間が吾輩のことをじろじろ見て通り過ぎていく。
ほんの気まぐれで、彼らから見えない丘の影に移動すると、人間たちがみな落胆したのが柵越しに伝わってきた。
ザマアミロと思いながら、吾輩は再びあくびをして冷たい地面に顎を落とした。
そのとき、人間たちがどよめいた。
何か面白いことが起きたのかと吾輩が首を上げると、人間の子供が丘の隅に倒れていた。怪我をしているように見える。どうやら吾輩を見ようとするあまり、柵から身を乗り出しすぎてここまで落ちてきたらしい。
吾輩は好奇心からその子供のそばに近寄る。
人間たちがざわめいた。
子供は顔を上げて、吾輩のことを見て悲鳴を上げた。
吾輩は驚いて「ニャア」と鳴いたが、そのせいで子供はさらに大きな声で鳴き出した。まったく、吾輩のような猫一匹に大げさな子供である。
そのとき、吾輩の面倒を見ている女がやってきて、吾輩をさらに小さな檻の中に移動させようとした。逆らっても後々面倒になるのでその誘導に従うことにした。その瞬間、上から覗いている人間たちに安堵の雰囲気が流れたのが分かった。
檻から眺めていると、倒れた子供は女があっという間に連れて行ってしまった。
女の仲間の別の人間が、生き物とは思えないような大きな声を出して壁の上の人間たちに何かを説明している。先が広がった筒のような道具を口に当てると、あのような大声が出せるのだ。
人間は説明の中で吾輩を指さして「ジャガー」という言葉を使ったが、吾輩のような猫にはその言葉の意味がとんと理解できぬ。
 勝負の理由
勝負の理由
あと少しのところで啓太は牛乳を吐き出してしまった。
食べかけの給食に牛乳がかかる。トレイの中だけなら良かったが、啓太の膝まで牛乳まみれだった。板張りの床に白い水たまりができていた。
その瞬間クラスメイトたちが歓声をあげ、決定的瞬間を見逃した者も、口と服を白く染めた啓太を見て何が起きたのかをすぐに悟ることができた。
啓太ははっとして正面の美弓を見た。ちょうどそのとき、彼女は空になった牛乳パックを高く掲げ、啓太に対してピースサインを向けたところだった。
「えっへっへー。またわたしの勝ちだね!」
悪いわねーと言いながら、啓太と美弓の机の境界線に置かれた「戦利品」のプリンを二つ、見せつけるように手に取った。彼女は戦利品をそのまま机の引き出しの中に入れる。
「あれ? 食べないの?」
同じ班の真一が美弓に尋ねると、美弓は一瞬だけ啓太の方を見て質問に答えた。
「うん。後で食べる。美味しいものはとっておくタイプなの。……それより啓太、早く牛乳拭いたら? 臭いよ」
そう言われてからも啓太はしばらく放心していた。やがて教室のロッカーから雑巾を引っ張りだすと、廊下にある洗面台へ向かった。
ひとまず口の周りを洗い流し、強烈な牛乳臭さからある程度開放されたところで、啓太の心には美弓に対する腹立たしさが猛烈に沸き上がってきた。
美弓とは幼稚園からの幼馴染だった。啓太は覚えていないが、美弓によれば啓太はずっと彼女にいじめられていたらしい。いくらなんでも自分をいじめていた相手のことを忘れるはずがないから、これはきっと啓太をからかうための美弓のでまかせだろう。
雑巾を絞りながら美弓に対する反発心を煮えたぎらせていると、隣で誰かが勢い良く蛇口を捻った。美弓が一緒に雑巾を絞っていた。
「何だよ」
「わたしも拭くの手伝う!」
「いらねえよ」
そう答えてから、牛乳まみれになった給食や服の始末のことを考えて啓太はうんざりした。
ぞんざいに断ったにもかかわらず、やはり美弓はそれでも啓太を手伝う気でいるようだった。
「……勝負に勝ったのはお前なんだから、別にそんなことしなくていいんだぞ」
「ありがと。でも早飲み勝負しようって言ったのはわたしだし」
「何の礼だよ。そのありがとってのは」
「別に」
上ずった声で美弓が否定した。
放課後、啓太がグラウンドから教室に戻ると、教室には真一とクラスメイトが数人残っているだけだった。
真一は啓太を見ていきなりむせた。
「何だよその反応。おい、何やってた」
真一が落ち着くのを待ってから啓太は問い質した。
「べ、別に何もしてないよ」
真一はまっすぐ目をそらさずに啓太のことを見ていた。それが逆に怪しい。
それからしばらく押し問答が続いたが、やがて啓太は、真一が机の引き出しにプリンの空き容器を隠していたのを見つけた。それも二つ、である。
「お前、なんでプリンなんか……」
「美弓にもらったんだよ」
「なんで美弓がお前にプリンをやるんだよ」
そのプリンは、まさに啓太と美弓の勝負の結果であるはずだった。真一はしばらく曖昧な返事を続けていたが、啓太を誤魔化せないと悟ったのか簡潔に理由を話した。
「美弓はプリンが嫌いなんだよ」
啓太は真一の言葉を何度も頭の中で繰り返した。それが意味するところを何度も考える。
「……くそっ」
啓太は悪態をついた。しかし自分がなぜこんなに腹を立てているのか、誰にも説明できそうになかった。
美弓の居場所をクラスメイトに訪ねると、彼女はすでに帰宅したと教えられる。仕方なく啓太も家に帰ることにしたが、頭の中ではずっと美弓に浴びせる罵声を探していた。
 フラッシュバック
フラッシュバック
私は空気を求めて口を開けたり開いたりを繰り返した。口や目の中にシャワーの湯が入ったが、そんなものよりも私は空気を求めていた。
でも智則は首を締める手を緩めてはくれなかった。
智則の指が私の首の皮膚をぎりぎりと締め上げる。私は必死になって智則の手を引っ掻いたが、いくら彼の手に傷をつけても呼吸は一向に楽にならない。指の爪が剥がれて血が出ていたが、もはや私には痛みを感じる力も残っていなかった。そして――――――――
「退院おめでとう。会社の方はどうするの?」
「多分近いうちに復帰すると思う。リハビリはもう終わったから、あとは心の準備だけよ」
退院の日、私は職場復帰について母にこう答えた。
主治医の先生とリハビリを手伝ってくれた看護師の方に挨拶を済ませてから、タクシーを拾って母と一緒に病院を出る。運転手に私のアパートの場所を告げると、隣に座った母が不安そうな表情を見せた。
「ねえ、やっぱり一人暮らしやめない? またあんなことがあったら――」
「もう、お母さんは心配症なんだから。大丈夫、私だってもう懲りたんだから。もうあんな変な男を捕まえたりしないよ」
「でもねえ、あんたが死んだかもしれないって聞いたときはもう、お母さん心配で心配で……」
なおも食い下がる母をなだめているうちに、タクシーは私のアパートの前についた。
荷物を持ってひとりでタクシーを降りる。
「それじゃあねお母さん。向こうには今夜のうちに帰るんでしょ? お父さんによろしく言っておいてね」
母の返事を聞く前に私はドアを閉めた。タクシーはまだ何か言いたそうな母を乗せて空港の方へ走って行った。
私はアパートの鍵を開けて、部屋の中に入った。
実に半年ぶりの我が家だった。最後にここに来たとき、私は智則に殺されかけたのだ。
自分では気にしていないつもりだったが、やはり部屋に戻るとあのときのことを思い出してしまう。息が苦しくなった気がしてブラウスのボタンを一つ開けた。
部屋の埃を追い出すために窓を開ける。雑巾を絞って、テーブルの上や台所を掃除した。私が入院している間に母がある程度は維持してくれていたようだが、以前私が使っていたときとまったく同じ状態にするのにはもう少し時間が必要だった。
夕方になる前に掃除は一段落した。夕食のことを考えなければならないが、その前に私は汗を流すことにした。
服を脱いで浴室に入る。
熱いシャワーを出して体に浴びた。
髪を湯で濡らしながら、私はあの日のことを思い出していた。
シャワーの音の向こうに、玄関の鍵を開ける音が聞こえた。智則が帰ってきた音だった。
「智則? おかえりー!」
あの日、私は髪を洗いながら玄関に向けて言った。
あのときはたしか、シャワーの音がうるさくて、彼の足音は何も聞こえなかったのだ。だから次に聞いたのは、彼が浴室のドアを開けた音だったはずだ。
「智則? どうして――」
智則は私を浴室の床に押さえつけた。
待って。ありえない。だって今は、もう――。
私は智則に首を締められた。それは私が殺されかけたときの記憶だったはずだ。今は一人でシャワーを浴びている。智則が私の首を締められるはずがない。
私は空気を求めて口を開けたり開いたりを繰り返した。口や目の中にシャワーの湯が入ったが、そんなものよりも私は空気を求めていた。
私は浴室を出た。ここには私一人しかいない。だってあの出来事は半年前に終わったことなのだから。――でも智則は首を締める手を緩めてはくれなかった。呼吸が苦しくなる。首の周りを指でなぞる。そこに智則の手はない。智則の指が私の首の皮膚をぎりぎりと締め上げる。締められているのが私の首なのか、半年前の記憶の中の私の首なのか、分からない。
そういえば、事件の後、智則はどうなったんだろう。警察に捕まった? そうに違いない、と思う。しかしその光景が思い出せない。被害者の私がそのことを知らないはずがないのに。そもそも私はどうして助かった? 誰かが助けに来てくれた? あんなにも死にかけていたはずなのに。
タオルで髪を拭いた。私は必死になって智則の手を引っ掻いたが、いくら彼の手に傷をつけても呼吸は楽にならない。首を拭いたとき、鏡に映った自分の首に赤黒い痣が浮かんでいるのが見えた。
智則の手の甲を何度もひっかくと、爪が剥がれて血が出たが、痛みは何も感じなかった。首を拭いたタオルに目を落とすと血で真っ赤に染まっていた。タオルを持つ私の爪は醜く剥がれて、そこから血が吹き出していた。でも私には痛みを感じる力も残っていなかった。
ああ、そうか。
私はまだあの日にいて、ずっと智則に首を締められていたんだ。
――――――――智則の手を引っ掻いていた私の手は力が入らずに床に落ち、酸欠のせいでところどころ穴の開いていた視界は完璧に白く埋め尽くされた。
私が最後までずっと見ていたのは智則の目だった。昏くて深い、闇のような……